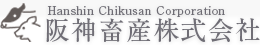マルチプルサイトシステム・スリーサイトシステム
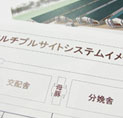
世界でも最先端の生産システムであるマルチプルサイトの考え方を取り入れた北広島農場(繁殖)、西城農場(離乳・肥育)と御調農場(離乳・肥育)を2011年にオープン。
阪神畜産では積極的に新たな生産システムをつくりあげています。
<スリーサイトシステムとは?>
繁殖・離乳・肥育といった役割に農場を分けることで、役割に特化した設備や業務に集中できるため生産効率が高まるほか、生産段階ごとの農場間に距離を置くことで、病気の蔓延を防ぐことができる生産システムです。
<マルチプルサイトシステムとは?>
世界で少しずつ広まっている最先端の生産システムです。繁殖・離乳・肥育に分けるほか、それぞれを複数農場持つことで、トラブルがあった場合に、豚を移動させクリーンな農場をすぐに立て直せるようにしておくことで、病気のリスクをもっとも減らせる生産システムです。
病気と闘わないための防疫標準作業書

すべての農場で防疫標準作業書を準備。たとえば人の入場にあたっては、毎回シャワーを浴びて指定の作業服に着替えたり、電気工事が必要な際には、外部の事業者が器具を持ち込まなくても済むように、必要な工具は農場内にあらかじめ保管しておき、やむなく持ち込む工具については燻蒸(くんじょう)処理を施し殺菌を行うなど、農場内に病気が入るリスクを徹底的に排除しています。
米国と欧州で実績のある2種類の育種導入

平均的な日本の農場では、年間に母豚1頭から離乳する仔豚が20頭。出荷する肉豚が18頭と言われています。対して阪神畜産グループでは、離乳する仔豚の頭数が26.5頭。出荷する肉豚の頭数が24頭以上となっています。ただし、これで満足するつもりはありません。目標は高く、1頭の母豚からの離乳頭数30頭、出荷頭数28頭をめざしています。そのために必要なのが育種。これまで扱っていた米国で実績があり産肉性に優れたPICに加え、欧州で広く流通し、多産性に優れたオランダ原産のTOPIGSを扱っていきます。
豚の育成段階に合わせ8種類の餌を使い分ける

阪神畜産の最も強い部分であると言っても過言ではないのが飼料要求率。飼料要求率とは、豚が1キロ増体するのに何キロ餌が必要なのかを表す単位。具体的な数字は企業秘密になりますが、常に全国でもベスト10(※1)に入っているほど。通常の養豚事業ではおよそ4~5種類の餌で一頭の豚を育てるのに対し、阪神畜産の場合は8種類の餌を成長ステージに合わせて使い分けています。豚がまだ小さな時期には、筋肉と骨の発育を促す高蛋白でカルシウムやリンを含んだ栄養を与え、大きくなると豚肉の味をつくるためのデンプン質の多い穀物を増やす。このように、豚の発育時期に合わせ8種類の餌を使い分けることで効率的な栄養を供給できるため全国でもトップクラスの飼料要求率を実現しています。良好な要求率は限られた世界の穀物資源の有効利用にも寄与します。(※1)生産成績管理ソフト「ピッグチャンプ」調べ
暑い夏も、寒い冬も、快適に過ごせる環境づくり

環境づくりにとって大切なのは、人間を基準に考えるのではなく豚を基準にして考えるということです。たとえば人間の目線の高さにある温度では、作業する人間に都合の良い気温であり、もっと低い位置にいる豚にとって快適な気温とは限りません。豚にとっての適温は、季節や湿度、そして周囲の空気の流れなど、周囲の環境に左右されるもの。特に離乳豚舎にいる仔豚の場合は体温調節機能が未熟ですので夏場や冬場の温度管理はとても大切。阪神畜産グループでは、換気扇や空調設備を使っての環境管理はもちろんのこと、豚を観察しストレスの兆候が現れていないかをいち早くチェックできるようにしています。
生産性を偶然任せにしない人工授精

阪神畜産グループの交配手法は人工授精。欧米では9割の豚が人工授精で生まれるのに対して、日本では3割しか人工授精を行っていないのが現状です。そこで阪神畜産グループは生産性を高めるために国内でもいち早く人工授精を取り入れています。また、精液の採取から希釈、充填までの全ての製造工程を自社の人工授精センターで行います。一貫して自社で豚の繁殖を行っていくことで、さらに高い生産効率をめざしています。
生産しながらすべての豚舎で実験できる

離乳、肥育など各農場への移動にあたっては、トラックスケールで各ロットごとの体重を測定。さらに豚が食べる飼料の種類や量を管理しているため、すべての豚舎で各ロットごとの育成データを取得できるようになっています。よりよい豚の飼育方法や生産性の向上を追求する取り組みの結果が、具体的な数字として見えるので、長年の経験に頼らなくとも効率的に技術向上を図れる仕組みが整っています。あたかも、大学の実験室が生産現場になるかのような施設があります。
データに基づく飼育情報の管理

すべての農場では、豚の育成データを事務所でモニタリング管理。豚の育成データはもちろん設備の運用データまで、あらゆるデータを一元管理しています。また、過去5年間の温度データを保存するなど、長期間に渡る観察データがあるため、さまざまな角度から分析を行うことが可能です。